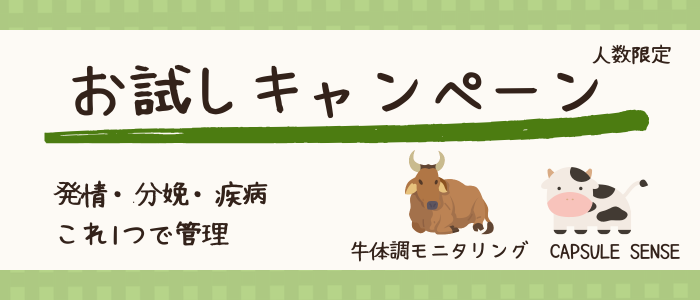牛の健康を守る削蹄の重要性や具体的手順、安全管理のポイントを分かりやすく解説しました。
日本各地には多様な畜産業が存在しますが、酪農が盛んな地域では、乳牛の健康を守る「削蹄」が大きな注目を集めています。牛の蹄(づめ)は体のわずかな部分ながら、大柄な動物である牛の体重を支える重要な役割を担うため、定期的にケアをすることで病気を予防し、健全な状態を保てるのです。農家や法人といった形で経営を行う立場の方だけでなく、酪農に関する知識を深めたい方にとっても、削蹄技術の理解は大きなメリットをもたらします。
牛の健康を守る「削蹄」作業、その重要性とは?
牛の健康を維持し、酪農の安定した生産を目指すうえで削蹄は欠かせません。年2回の削蹄が一般的ですが、コンクリートなどの飼育環境では、蹄角質が過度に伸びて形がアンバランスになりやすい傾向にあるため、年3~4回の削蹄を行う牧場も増えてきています。歪んだまま放置すると足への負担が増大し、蹄病などの病気の原因になります。適切に整えられた蹄は歩行を安定させ、乳牛の生産にも良い影響をもたららすため、牛の健康リスクを抑えながら畜産経営の効率化を高める事に繋がります。

牛はなぜ定期的な削蹄が必要になるのか
大柄な牛の体重は600キロを超える場合も多く、わずかな蹄で支えているため、削蹄の重要性が高まります。適正な角度に整えることで足腰への負担を軽減し、健康や生産性を保ちやすくなります。月に数回の訪問でこまめに管理する削蹄師もいれば、年に数回まとめて作業する方法も存在し、牧場の方針や環境に合わせて計画的に実施することが大切です。
削蹄を怠った場合、牛の健康にどんな影響が出るのか
削蹄を行わないまま放置すると、伸びすぎた蹄が変形し、牛の足に大きな負担を与えます。実際には月におよそ5ミリずつ伸び続ける蹄を、コンクリート上で酷使し続けると変形が進行しやすく、痛みや蹄病へのリスクが高まります。深刻な状態に陥ると生産性の低下にも直結し、大きな損失に繋がる恐れがあります。

削蹄管理を円滑に進めるポイント
削蹄には特殊な刃物や鎌(ナタ)のような道具が使用されます。安全対策として、削蹄枠などで牛を動かないように固定し、一連の作業をスムーズに行う方法が一般的です。必要なときに相談できる削蹄師や獣医師との連携を図り、牛の状態をこまめに確認することが、健康で安定した生産へとつながります。
<削蹄管理2 つのポイント>
・定期的な削蹄スケジュールを立てる
・早期発見のために日々観察を欠かさず行う
定期削蹄の実施と並行して、牛床の掃除や飼育スペースの改善に取り組むことも効果的です。湿った床や滑りやすい場所があると、牛が足を痛めるリスクが高まります。酪農や畜産に関わるスタッフ全員が、牛の健康を最優先に考えて行動することが、より良い結果をもたらします。
最新の研究と削蹄による乳牛の生産性アップについて
近年の研究では、蹄がきちんと整っている牛は乳量が多く、繁殖成績も良好であるとするデータが報告されています。足への負担が少ない状態を維持できると、飼育中のストレスが減り、食欲や歩行にも良い影響が及びます。農場規模の大小に関わらず、どのような形態であっても、定期的な削蹄による、牛の健康を守る意義は大きいといえます。
また、生産性向上や牛の健康維持だけでなく、「アニマルウェルフェア(動物福祉)」の観点からも「削蹄」は大切な作業の一つと言えます。足元を保護し、健康を維持することで、畜産の未来はより明るくなり、牛と人間の双方にメリットをもたらすでしょう。
削蹄は牛と酪農の未来を支える鍵
削蹄は、酪農における生産性向上や牛の健康維持だけでなく、動物保護の観点からも大切な作業です。牛舎の環境や牧場の方針に合わせて計画的に行うことで、足腰への負担を軽減し、乳量アップや病気予防につなげられます。今回紹介した削蹄に関する内容を押さえながら、あなたの地域や牧場での最適な飼育方法をぜひ模索してみてください。
牛を1頭づつ体調管理できる最新ICT機器「CAPSULE SENSE」
今回は「牛の健康維持」「生産性向上」に直結する”削蹄”についてご紹介させていただきましたが、繁殖農家・酪農農家の経営効率化において、牛の体調管理をすることは必要不可欠です。
最新ICT機器である「CAPSULE SENSE」は牛の体温と活動量を計測できる機器となっており、「24時間365日」、牛の体調をモニタリングすることが可能です。発情・分娩・疾病等を高精度で検知できるため、各農家の生産性向上に貢献できます。
只今、お試しキャンペーンも実施しておりますので、ご興味がある方は弊社ホームページからお問い合わせ下さいませ。